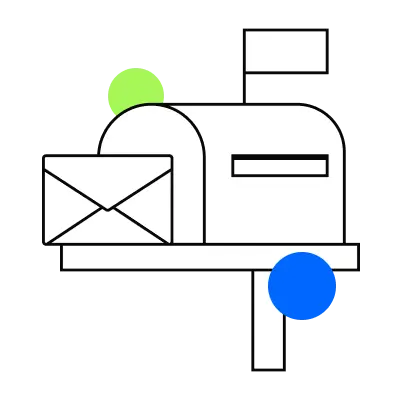99CENTSの検索結果
コース (0)
記事 (15)
用語集 (0)

クイックガイド:暗号資産の低閾値エアドロップの99%を確保する方法

Gate Research: イーサリアムメインネット収益が99%減少、日本銀行の利上げ期待が高まる

Gate ウォレットの包括的な分析:初心者がオンチェーン世界に入るための最適な選択

Gate ウォレットの包括的分析:ワンストップオンチェーン資産管理とDApp探索

gate Research:Ethereum現物ETF保有残高がレイヤー2の総保有残高を超え、Magic EdenエアドロップがNFT市場の復活を促進

セレブリティが支持するミームコインの背後にあるリスクと論争を1つの記事で理解する

効率性と安全性だけではない:GateウォレットがどのようにあなたのWeb3機会レーダーになるか?

Gate 研究:CEX からの連続的なステーブルコインの流出、EigenLayer がステーキングエアドロップの第二フェーズを開始

gate Research:MiCAが発効、gate Quant Fundは過去最高の38%の年間リターンを達成

ゲートリサーチ:BTCはATH近くで推移、ETHは$3,500を突破、Pump.funはライブストリーミングを中止

gate Research: BTCが91111ドルに下落した後、反発し、DeFi TVLが記録的な高値に達しました

gate Research: GTが史上最高値を記録、EthereumメインネットのStakingが54M ETHを超える

gate Research: トランプファミリーがイーサリアムエコシステムに参入、Aaveプロトコルが記録的な高いTVLを達成

Gate Research: Gate.ioが正式に新しい中国語名「Damen」を採用、イーサリアムステーブルコインの送金が1.18兆ドルに達し、OMフラッシュクラッシュ
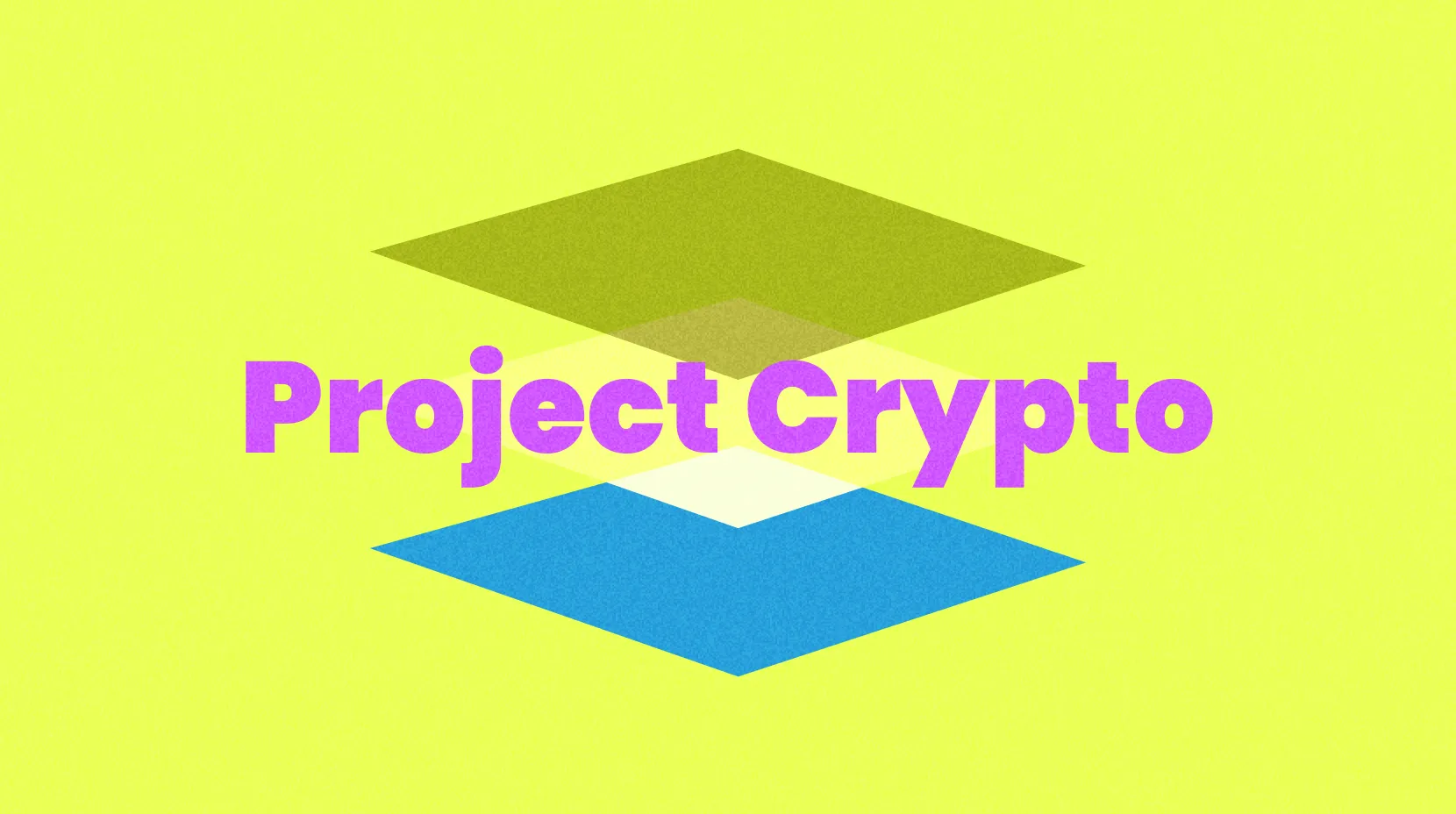
7月31日、米国証券取引委員会(SEC)は「Project Crypto」イニシアチブを発表し、金融機関が株式取引、暗号資産、DeFiサービスを単一のプラットフォームで統合できることを初めて認めました。この動きは、暗号資産分野におけるスーパーアプリの時代が到来することを示しています。Coinbase、JPMorgan Chase、Fidelityなどの大手プレーヤーは、業界構造の大きな変化に直面しており、DeFiプロトコルにとっても抜本的な再評価が必要となります。本記事では、政策フレームワーク、市場動向の変化、そして競争環境について総合的に分析します。さらに、新たなルール下でどのプレーヤーが競争優位を得るのか、反対に取り残される可能性があるのかを詳しく考察します。Project Cryptoは、暗号資産金融における「iPhone誕生の瞬間」となり得るでしょう。
7月31日、米国証券取引委員会(SEC)の新議長ポール・アトキンス氏が「デジタルファイナンス革命におけるアメリカのリーダーシップ」と題した講演を行い、新プロジェクト「Project Crypto」を発表しました。
この発表は現時点で大手メディアには取り上げられていませんが、2025年の暗号資産業界を大きく変える可能性のある出来事と言えるでしょう。
1月にトランプ大統領がホワイトハウスに復帰した際、米国を「暗号資産の世界的中心地」とすることを公約しました。当時、多くの業界関係者はこれを単なる選挙公約と受け止め、本当に実現するのか、それともまた口約束に終わるのか注視していました。
そして昨日、その答えが明らかになりました。
Project Cryptoは、トランプ政権の暗号資産推進政策の最初の本格的な具体化とみなされます。

新たな構想についてはSNSや各種メディアで多くの詳細が語られていますが、ここでは繰り返しません。最も注目すべきは、金融機関が1つのプラットフォーム上で株式取引、暗号資産、DeFiサービスなどを統合した「スーパーアプリ」を展開できるようになる点です。
仮にJ.P.モルガンのアプリで株式の売買、ビットコイン取引、DeFiのイールドファーミング等が全て一元的に利用できるとしたら、業界にどれほど大きな変革をもたらすでしょうか。
選挙のスローガンから規制実務への移行、そして「強制による規制」からオンチェーン金融への積極受容まで、わずか6カ月で一気に進展しました。世界最大の資本市場が方向転換すれば、業界全体の競争環境が根本から変わります。
オールインワン型スーパーアプリ
アトキンス氏によるスーパーアプリの構想は、中国で一般的なWeChatのように、メッセージ、決済、資産運用、保険、ローン申請といった機能を1つのアプリに統合するものです。
中国ではこのようなシームレスな体験が浸透していますが、自由市場を重視する米国ではほとんど例がありません。
その主な理由は、複雑な規制の壁にあります。
米国で決済業務を行うには決済ライセンス、証券業務にはブローカーディーラーライセンス、貸付業務には銀行ライセンスが必要であり、さらに州ごとに異なる規制も加わります。
Project Cryptoは、このような複雑な規制構造を初めて突破しました。
新たな枠組みでは、ブローカーディーラーライセンスを持つプラットフォームが、株式取引、暗号資産取引、DeFiレンディング、NFTマーケットプレイス、ステーブルコイン決済サービスなどを統一的なライセンス体制のもとで提供できるようになります。

暗号資産業界にとって、こうした一元的な枠組みは非常に大きな意味を持ちます。なぜなら、多くの暗号資産プロダクトの中核である「合成可能性」と本質的に親和性があるからです。
たとえば、株式の利益で自動的にビットコインを購入し、NFTを担保にステーブルコインを借り入れ、そのステーブルコインをDeFiでさらに運用利回りを得る—これら全てが1つのインターフェース上で、オンチェーン資産としてシームレスに展開できます。
ユーザーが単一プラットフォーム内で資産を自在に移動できるようになれば、本格的なWeb3型金融スーパーアプリの実現も射程圏内となります。
SECの今回の動きは、金融分野とテクノロジー分野の双方において新たな競争の幕開けとなるでしょう。
3タイプのプレーヤー、3方向の分岐
Project Cryptoの始動により、業界の主要プレーヤーの進路は分岐し始めています。
既存の暗号資産大手は、これまでの「イージーウィン」から激しい競争への転換を迫られます。
Coinbaseのブライアン・アームストロングCEOも、SECの訴訟から解放された安堵と、今後その独占的地位が揺らぐかもしれないという複雑な思いを抱いているでしょう。
皮肉にも、前任のゲンスラー議長による厳格な規制がCoinbaseにコンプライアンス面での優位性を与え、米国のユーザーにとって事実上のデフォルトとなっていました。
現在は、その「規制による堀」が消えつつあります。さらに厳しいのは、Coinbaseが単なる取引所から総合金融プラットフォームへと大きく舵を切る必要があることです。すなわち株式取引(Robinhoodとの競争)、銀行サービス(大手銀行との競争)、DeFi統合(分散型プロトコルとの競争)など、既得権益を持つ強力な競合が待ち受ける市場で戦わなければなりません。
KrakenやGeminiも同様ですが、むしろそれ以上に厳しい選択を迫られます。
Coinbaseほどの規模やリソースがなければ、彼らの多くは買収されるか、ニッチ市場へ特化せざるを得ない状況です。
暗号資産ネイティブ企業が自らの競争領域を守ろうとする一方で、伝統的金融大手は大規模な攻勢の準備を進めています。
J.P.モルガンは暗号資産に否定的とは限りません。同社のJPM Coinは日々数十億ドル規模の決済を担い、「Onyx」ブロックチェーンプラットフォームもすでに実績があります。今、J.P.モルガンは一般ユーザー向けに暗号資産サービスを正規に展開できるようになります。
ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、バンク・オブ・アメリカなどの大手銀行も同様に動いています。彼らは暗号資産企業が切望する巨大な顧客基盤、潤沢な資本、洗練されたリスク管理、そして—何より—公的信頼を有しています。
米国の年金受給者が年金でビットコインを購入したい場合、30年利用してきた銀行アプリと、知らない暗号資産取引所のどちらを信頼するでしょうか。
しかし、これら金融大手の組織変革は決して容易ではありません。官僚的慣性、レガシーITシステム、保守的な企業文化が障壁となります。銀行側にとって新たな規制は、機会であると同時に新たな試練です。
DeFiプロトコルのUniswap、Aave、Compoundなどにも独自の課題が生まれています。
Project Cryptoは「純粋なコード発行者」を明確に保護しており、理論上はDeFiに有利なはずです。
ですが、CoinbaseがUniswapの機能を直接統合したり、J.P.モルガンが独自のオンチェーンレンディングを提供するようになった場合、分散型プロトコルとしての固有価値はどこに残るのでしょうか。
1つのシナリオとしては、「プロトコル層」と「アプリ層」の明確な役割分担が考えられます。Uniswapが基礎流動性を提供し、スーパーアプリがその上でユーザーインターフェースや高付加価値サービスを展開するイメージです。これはインターネット時代のTCP/IPのような、目立たないながらも不可欠な基盤に例えられます。
さらにラディカルなシナリオとしては、一部のDeFiプロトコルが中央集権的な運営に舵を切り、企業化・規制順守・ライセンス取得を積極的に進めて市場拡大を狙う可能性もあります。
Aaveは既に機関投資家向けバージョンをテスト運用し、Uniswap Labsも法人組織化されています。分散化という理想は魅力的ですが、ライセンスを取得した競合が数億人規模にリーチできれば、その理想は単なる標語で終わるかもしれません。
結果的にDeFiは、「プロトコル純粋主義者」と「現実主義的な成長志向」の2つに分かれる可能性があります。どちらの路線も存続可能ですが、ターゲットとなる利用者層は大きく異なるでしょう。
3つの主要プレーヤーにそれぞれ異なる道がありますが、共通しているのは「これまでの安定領域を失った」という事実です。
全ての企業が、新しいエコシステムにおける自らの役割を再定義しなければならなくなりました。
業界の主戦場—4つのキー・ディメンション
全プレーヤーが同じフィールドに立った今、勝敗を分けるのは何でしょう。
まず何より重要となるのは「ライセンス」です。
これまでコンプライアンスは「底なし沼」とされてきましたが、現在は最大の参入障壁になるかもしれません。
Project Cryptoは一見ハードルを下げたようにも思えますが、実のところ参入基準を引き上げています。スーパーアプリ・ライセンスを取得するには、証券・銀行・決済・暗号資産などの多岐にわたる規制をクリアする必要があり、真に実力のある事業者だけが参入できる土俵です。
ライセンスの価値はネットワーク効果にあります。ユーザーがすべての金融ニーズを1つのプラットフォームで解決できれば、乗り換えコストが高騰します。かつての銀行と同じで、誰もが申請できても帝国化できるのはごく一部です。
次に重視されるのはテクノロジーアーキテクチャです。
オンチェーン金融にはWeb2レベルのスムーズさとWeb3のユーザー主権を両立させることが必須条件です。これは非常に難易度が高い要求と言えるでしょう。
伝統的金融機関は暗号資産インフラをゼロから構築しなければならず、暗号資産企業は銀行同等の堅牢な信頼性を求められます。
クロスチェーン対応はさらに高いハードルです。たとえばEthereumからSolanaへの資産移動を3秒で実現できるか。激しい市場変動時にリスク管理をミリ秒単位で実行できるか。
技術的負債は大きなリスク要因です。
Coinbaseは10年かけて単一機能の最適化を図ってきました。全面的な金融プラットフォームへ転換するのは非常に困難です。銀行のレガシーシステム(COBOLなど旧式技術を含む)とも連携が求められますが、これをブロックチェーンとどう接続するかは大きな課題です。
3点目は流動性です。
金融において流動性は最重要の要素であり、スーパーアプリ時代ではその重みが一層増します。
ユーザーはどの資産でも、いつでも、好きな金額を即時に取引できることを期待します。そのためにはグローバル全主要取引所の流動性を集約し、資本効率を最大化しなければなりません。1つの資金プールで株式・暗号資産・DeFiをシームレスに取り扱うには、極めて高い運用能力が問われます。
4点目はユーザーエクスペリエンスです。
最も過小評価されがちですが、機能や価格が各社で均衡した場合、決め手となるのは体験です。
課題は、多様なユーザー層をどう満足させるかです。暗号資産の熟練者は完全なコントロールやオンチェーンデータを望みますが、従来型ユーザーは「シードフレーズ」といった用語すら知らないかもしれません。1つのアプリで2つの世界観を両立させるには、製品運営面で高度なバランス感覚が必要です。
まとめると、Project Cryptoは業界にとって新たな試練です。ライセンスが事業範囲を、テクノロジーが品質を、流動性がスケールを、ユーザー体験が到達範囲を決めます。この多次元的な競争での一手一手が、市場を大きく変えるポテンシャルを持ちます。
ポテンシャル・ウィナーとロス—新たな勝者と敗者
Project Cryptoによって誰が大きく勝つのか、多くの関係者が関心を持っています。
ただし将来予測に絶対はありませんが、浮かび上がるのは新たなトレンドです。スーパーアプリ時代の勝者像は画一的ではなく、3つの成功モデルが想定されます。
第一は「アライアンス(同盟)モデル」です。
最も戦略的なリーダーは、単独行よりもパートナーシップを重視します。
たとえばFidelityは11兆ドルの資産を持ち、2018年にデジタル資産部門を立ち上げましたが、リテール暗号資産取引では大きな成功を収めていません。
もしFidelityがFireblocksのような大手暗号資産テック企業と緊密に連携すれば、2億人のクライアントにシームレスな暗号資産体験を提供でき、パートナーも信用とユーザーを獲得できます。この2社に限らず、こうした「1+1>2」の提携が今後増加するでしょう。
第二は「武器商人モデル」です。
急成長市場では基幹インフラの提供が最も着実なビジネスモデルです。
スーパーアプリ時代の「シャベル」はインフラそのもの。Chainalysisの例のように、誰が勝ってもコンプライアンスツールを必要とするため、中立かつ不可欠な立場で全陣営にサービスを提供し成長できます。
第三は「スペシャリストモデル」です。
全ての企業が万能型を目指す必要はありません。DAO特化、NFTファイナンス特化など特定領域に絞ったプラットフォームも現れるはずです。大手が総合プラットフォーム構築に動く一方、スペシャリストは独自分野で長期的な成長を狙えます。
敗者となるのは、規模が中途半端な金融機関や真ん中に取り残された投機主体です。
米国の地方銀行などはJ.P.モルガンほどのIT投資力も、フィンテック新興企業ほどの機動力もありません。大手がフル機能の暗号資産サービスを展開すれば、中堅プレーヤーは苦境に追い込まれます。
一方、規制逃れを目的に複雑な法的枠組み(ケイマン籍、DAOガバナンス、「完全分散化」主張)を用いたプロジェクトも多く見受けられます。
Project Cryptoの明確なルール整備により、そうしたグレーゾーンは排除されていくでしょう。「完全分散」を選べば流動性やUXに制約、「完全準拠」を選べば規制コストが課題となり、「どちらつかず」はもはや許されません。
ビジネス面では、最適なタイミングで動くことが非常に重要です。
プラットフォームドリブン市場ではファーストムーバーの優位性が決定的です。今後数カ月で完全なエコシステムを構築できる企業が、次世代の暗号資産金融を牽引する存在となるでしょう。
iPhoneモーメント—暗号資産金融の転換点か
2007年、スティーブ・ジョブズが初代iPhoneを発表した際、ノキアの経営陣は「誰がキーボードなしの携帯を使うのか」と一笑に付しました。しかし18カ月後、業界構造は劇的に変化しました。
Project Cryptoは、暗号資産金融にとってのiPhoneモーメントになる可能性を秘めています。
それは完璧なものだからではなく、主流金融機関が初めてその潜在力を目の当たりにできるからです。金融サービスの新たな形、伝統資産と暗号資産の真の融合、コンプライアンスとイノベーションの両立が現実的な選択肢となります。
ただし、iPhoneが本当に社会を変えたのはApp Storeが登場してからでした。Project Cryptoはいわば始まりに過ぎず、本質的な転換点は業界エコシステムが成熟した時に訪れるでしょう。
何百万人もの開発者による新サービス、何十億人ものユーザーによるオンチェーン金融の大規模利用—それが起きて初めて本当の変革時代が到来します。
よって、現時点で結論を下すにはまだ早すぎます。
免責事項:
- 本記事は [TechFlow] より転載しています。著作権は原著者 [TechFlow] に帰属します。転載に関してご懸念がある場合は、Gate Learn チームまでご連絡ください。速やかに対応いたします。
- 免責事項:本記事の見解・意見はすべて著者個人のものであり、投資助言を目的としたものではありません。
- 各国語版はGate Learnチームによる翻訳です。Gateが明示的に出典を示していない限り、翻訳記事の無断転載・配布・盗用を禁止します。
暗号資産の世界へのゲートウェイ、Gateに登録して新たな視点を手に入れましょう